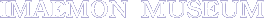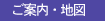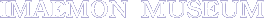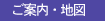|
手のひらに収まる程の小さい小皿である。父・十三代はかねてから、「古陶器の中で、ひとつ買っていいと言われたら、どんなもの買うか」と聞かれたときに、「手のひらに収まるぐらいの掌(たなごころ)の良いものがいいな」と言っていた。手のひらで撫で回しながら、にこにこして話す姿が目に浮かんでくるようである。この変形皿を手に入れたときも、ことのほか喜んでいた。それが銹釉ときたから、ほんとに嬉しかったのだと思う。父は、初期伊万里が好きであったが、特に銹釉の発色に魅かれていたようである。そのため、20代から30代にかけての作品には銹釉の掛け分けの作品が多い。その憧れが薄墨の技法に結びつくのだと思っている。
この皿は、銹釉なのか黄釉なのかは判らないが、どちらにしても、釉薬の中の鉄分の作用であるが、いつ見ても引き込まれる程の発色である。お正月に向けて、美術館に飾りたいと思っている。
(文・14代今泉今右衛門)
|