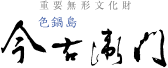色鍋島と今右衛門の現代 (3)
この文章は2006年雑誌「炎芸術 No.86」にて14代今右衛門がインタビューを受けた内容です。
インタビューその3
色鍋島の「伝統」
編集部(以下◆)常にこうした「雪文」文様や「雪花」技法のような新しい展開をはかっていくということは、色鍋島の伝統なのでしょうか、またそうしなければならないものなのでしょうか?
今右衛門(以下◇)色鍋島は、江戸時代には基本的に藩の庇護のもとで、藩窯による成形・下絵付けと御用赤絵屋・今右衛門の上絵付の分業で作られてきました。それが明治になって、藩の保護がなくなり、赤絵だけではなく素地からすべての制作に乗り出し、十代の頃から大変苦労して今右衛門窯の基礎を築き上げてきました。
そして十代・十二代と色鍋島の伝統的な技術を継承する中で、その時代の最高のものを造ろうと努力してきましたが、新しい時代の色鍋島を、自分の独創的な美意識を持って造ろう、また造らなければならないという考え方は、十三代になってから始まったものだと思います。ただ、それぞれの時代において認められる最高の色鍋島を造り上げるという姿勢では、ずっと繋がっていたと思います。
◆ 十四代の作品を見ていますと、現代の色鍋島をどう作るのか、という命題を強く意識していらっしゃるという感じを受けましたが、いかがでしょうか?
◇ 父・十三代から、伝統という仕事は、技術を継承していく中で、その時代のものを作るという「新しい仕事」なんだ、と常に言われてきました。
江戸時代の色鍋島や古伊万里を見てみましても、実は何かを遺そうという気持ちではなく、その時代時代で求められているものをどう造っていくかということの繋がりのように感じます。注文があれば、それによって文様も技術も変わっていくというやり方なのです。結果的にそれが時代に向けた仕事だったと思います。
◆ 現代のデザイン感覚から見ても、色鍋島の文様は、非常に斬新で「現代的」なものを持っていますね。例えば大根を皿いっぱいに描いたり唐草などのアラベスク文様をバランスよく配置したりとか、これは元禄年間に完成する「和様」のデザインとも共通するように思います。
◇ 色鍋島の源流は、中国の明代成化年間の景徳鎮官窯で完成し、清代にも盛んに作られた「闘彩」(とうさい)にあると昔から言われています。
闘彩というのは、青花(染付)で線描きして、上絵で色をつける技法で、気品高い色絵磁器です。その美意識を基として、京都の染織などの文様を参考にしたのではないでしょうか。おそらくその意匠は、当時の京都の文化や工芸品などに詳しいデザイナーが鍋島藩の中にいて、その指示で職人に描かせたものではないかと思っています。
◆ なるほど、そうして完成されていった色鍋島様式というものを、現代の今右衛門窯では当代がアートディレクターとなって、どうアレンジして使っていくかをディレクションされているわけですね。
◇ そうです。ただ、絵柄によっては十一代の頃からずっと変わらずに造っている文様もありますし、現在では自分のデザインのものもあります。
◆ 個人の陶芸家が自由に自分の思うままの絵付をするのとは違って、個人作家としての十四代と今右衛門窯の当主という二つの役目を背負っていることは、制作の上で非常に重要な意味を持っているわけですね。
◇ 個人作家の作品と窯元としての作品という区別もありますが、やはり十四代今右衛門として、現代の色鍋島をいかに創り上げるかという、それは色鍋島の継承者であるという意味合いが強いと思います。
色鍋島というと、染付で輪郭線を描いて、それに赤・緑・黄の上絵で色を付けていく、という定番のイメージでよく言われますが、昔のものにも他の色や金彩があったり、無釉や白化粧があったり、青磁や墨はじきも技法もあります。鍋島の世界で、何をしてはいけないということはないのです。間口としては広い世界だと思います。
◆ 十三代が革新的な方で、色鍋島の間口を広げたという意味でも功績があったと思いますが、その後ですからプレッシャーもかなりあったのではないですか?
◇ 正直に言えば、父が亡くなって、十四代を襲名したときに、襲名展の作品をどうしようかということよりも、職人さんたちをいかに守っていこうかということの方が心配でした。
◆ 重要無形文化財の保持団体の指定を受けるほどの名門の窯元であり、分業システムもしっかりしていて、技術的にも申し分のないような職人さんばかりでしょから、その集団をまとめていくことは大変な仕事ですね。
◇うちは男は兄と二人兄弟ですが、祖母がよく、男二人なので、作る方と売る方と、力を合わせて今右衛門を盛り立ててくれるといいね、と話していました。ですから、窯元としての営業面は兄が見てくれています。
(その4へ続きます)
(「炎芸術」 2006年No.86号より)