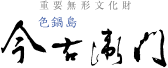色鍋島と今右衛門の現代 (4)
この文章は2006年雑誌「炎芸術 No.86」にて14代今右衛門がインタビューを受けた内容です。
インタビューその4
十四代今右衛門の「現代」
編集部(以下◆)そこで襲名展のときには、色鍋島という伝統のものをうまく継承していくことと、そこに自分のオリジナルなものを付け加えて行かなければならないということになるのですね。
今右衛門(以下◇)自分としては、襲名のときに、自分独自の新しいものを作らなければいけないというようなことはあまり考えませんでした。父が30年もかけてやってきたことを、そう簡単に出せるものではないと思っていました。
ただ、会う人ごとに、十三代は「吹墨」(絵の具を霧吹きなどで素地に吹き付ける技法。初期伊万里からあるが、十三代は呉須や薄墨を使った)をやられたが、十四代は何をやられますか、などと言われ、かえって自分は何か新しいことを出さなければいけないのだろうか、とも思いました。
そのような中で、襲名展の4ヶ月前には3分の1ほど出来上がっていましたが、自分でも今ひとつしっくりこないところもありながらの制作でした。
◆ 色鍋島としての今右衛門と十四代の今右衛門とのバランスですね。
◇ そのとき、東京から来られた評論家の先生に、ぜひ作品を見てくださいとお願いしたんです。そうしたら「なんだこのゴチャゴチャしたものは、こんな作品は鍋島でも何でもない、こんなものを出してもしょうがない、全部造り直しなさい」と言われて、造り直せと言われても、と思ったのが正直なところです。
自分でも引っ掛かっていたのは、こうすれば色鍋島に見えるとか、これを入れれば十三代と違う感じになるとか、そんなことばかり気にして制作していたんですね。理屈ばかり考えて造ったような気がします。それで、もう一度原点に帰って、自分の表現したいものを造ってみよう。鍋島とはとか、十三代との違いとか考えず、人から何と言われようと、自分の表現したいものだけで造って行こうと決め、それからスーと作品が造れたような気がします。
◆ 結果的にはやはりそれがよかったのですね。色鍋島としても十四代の個展としても、好評だったと思います。
◇ 襲名披露展でも何点かが売れ残りましたが、バブルの時代、若手作家の個展で、完売の連続だったそうですが、藤本能道先生(色絵磁器・人間国宝)の言葉で「完売ということは、その作家にとって何の意味もない。売れ残った作品がその作家を育てる」とよく言っておられたと三越の方からお聞きしました。
たしかに残った作品を見てみると、変な自分の理屈ばかりで造っているんですね。この文様はシンメトリーにしようとか、ここに角をもってこようとか、そんなことばかり考えて造った作品は、やはり人の心を打つことはできない。技術が未熟であっても、自分の思いを込めて造ったものは人に思いが伝わったような気がします。
◆ それは一人の作家という立場にしても、非常に含蓄のあるお話ですね。
さて、襲名披露展も一巡し、個展での新作発表も始まっていますが、最後に、十四代として今後、現代の色鍋島の可能性をどのように考えていらっしゃるのかをお聞きしたいと思います。
◇ 造りながら方向性を見つけていくということもありますが、現在は、自分の中にある「抽象」という世界と色絵・文様とをいかに一体化させていくか、というようなことを考えています。
昨年、「華」というテーマをいただいた日本橋の壺中居での展覧会に、百合の花の形をした花瓶や鉢を発表しました。これも色々と試行錯誤を繰り返しましたが、最後にやっと抽象的な形状の中で文様を表現することができました。この方向を自分の中でもう少し追求して行きたいと思っています。
◆ 実にモダンな形ですが、花びらの曲がり具合が難しいでしょうね。しかもその形が、内側の「雪花」と外側の「雪文」の文様によく合っていて、器としてだけでなく、オブジェのようにも見えますね。
◇ 実は、こういう百合の花の形をした小鉢は昔の色鍋島にあるんです。形はもっとリアルな百合の花びらになっています。それをヒントに、ロクロの型打ち技法を使って、現代的な形状を目指して造って行きました。
◆ 作家の自由気ままな造形というのではなく、それが色鍋島の「品格」に合っているかどうかということが難しいところですね。
◇ 作品というのは、十四代の作品であれ窯元の作品であれ、人を豊かにするものでなければならない、ということが基本にあると思っています。作家個人の作品は、自分の理念や思いをものに託して、いかに人に伝えるかということですが、デザインの世界は、人が最初にいて、その人を豊かにするようなものをいかに造るのかということで、出発点が違うだけではないかとも思います。
◆ 十四代のお話は、これからも自信を持ってもの造りを進めて行けるという姿勢の現われだと思います。
今後の展開を楽しみにさせていただきます。どうもありがとうございました。
(「炎芸術」 2006年No.86号より)