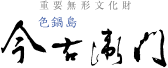か行
-
■ 窯(かま)
焼物を焼くための焼成炉。素焼、本窯、赤絵窯があり、焼成温度・窯の構造もそれぞれ違ってくる。今右衛門の本窯は現在も、昔ながらの薪を使う窯で焼成している。
-
■ 貫入(かんにゅう)
釉面にみられるひび。素地と釉薬の収縮率の違いからおき、装飾のひとつとして使う場合もある。
-
■ 素地・生地(きじ)
成形された焼物の土。素焼焼成前を生素地(なまきじ)、素焼後を素焼素地と呼ぶ。
-
■ 金彩(きんさい)
金泥・金箔などを用い、施した華やかな装飾技法。
-
■ 金襴手(きんらんで)
色絵などに金彩を施した豪華絢爛な色絵磁器。中国・明の緑地金襴手・黄地金襴手が有名である。
-
■ 櫛目高台(くしめこうだい)
鍋島の作品にのみ見られる高台の文様。高めに造られた皿の高台に、染付で精巧に施された櫛のような文様。
-
■ 蹴轆轤(けろくろ)
足を使い、蹴って(足で引く場合もある)回転させる轆轤。
-
■ 古伊万里(こいまり)
伊万里焼の中でも、江戸期に造られたものを古い伊万里として古伊万里と呼ぶ。
-
■ 高台(こうだい)
器の底につくられた台のこと。削り出しによる高台と、土を後からつける付け高台の二種類の技法がある。鍋島では高台を高く造り、そこに櫛目高台、剣先高台など様々な文様が施されている。
-
■ 呉須(ごす)
染付に用いる絵具の鉱物の原料。釉薬を掛けて焼成すると藍青色に発色する。江戸期に使われていた天然の呉須は、現在、世界的に枯渇している。
-
■ 呉須赤絵(ごすあかえ)
赤や緑の上絵を主に色鮮やかに、豪快に描かれた中国・明代後期の色絵磁器。
-
■ コバルト(こばると)
染付に用いる絵具の科学的鉱物の原料。19世紀ヨーロッパから輸入され、呉須の不足とともに有田に於いても使われはじめ、現在では有田のほとんどでコバルトを主原料として調合し、染付として使われている。
-
■ 粉引(こひき・こびき)
白化粧とも呼ばれる。白泥で化粧掛けを施したもので、粉を引いたように見えることからこう呼ばれる。14代今右衛門の雪花墨はじきはこの粉引を墨はじきではじいた技法である。
-
■ 御用窯(ごようがま)
江戸時代につくられた藩窯のこと。藩が献上品などを造らせるために開いた窯。