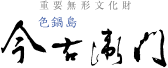た行
あ行 |
か行 |
さ行 |
た・な行 |
は・ま・や・ら行
-
■ 濃み(だみ)
塗ることを有田では濃みという。下絵の染付の濃みと、上絵の色絵の濃みがある。有田では、染付の濃み筆は太い特有の筆を昔から使っている。
-
■ 土型(つちがた)
土でつくられた成型用の型のことで、型打ち技法・糸切細工のとき使われる。現代では石膏でつくられることも多い。
-
■ 陶器(とうき)
粘土を主原料とし、非透光性で若干の吸水性がある焼物。主な産地としては、唐津・萩・備前・信楽・常滑など。
-
■ 陶工(とうこう)
陶磁器の制作に携わる人。
-
■ 陶土(とうど)
陶器の原料になる土。
-
■ 透明釉(とうめいゆう)
1300度前後の還元炎焼成により透明になる釉薬。鍋島では柞灰を主原料として調合する。
な行
-
■ 鍋島(なべしま)
江戸時代、佐賀鍋島藩が築いた、献上品専用の御用窯で造られた焼物。色絵磁器を中心として染付、青磁、銹釉、瑠璃釉などがあり、本窯焼成までを伊万里の大川内で造り、赤絵付けは今右衛門によって代々絵付けされた。
-
■ 錦(にしき)
赤・緑・黄・紫・青などの多彩な上絵付けを施した色絵磁器のこと。
-
■ 登り窯(のぼりがま)
斜面を利用し、いくつかの焼成室を連結した窯。朝鮮半島から伝わり、17世紀以降有田を含め各地に広がった。
あ行 |
か行 |
さ行 |
た・な行 |
は・ま・や・ら行